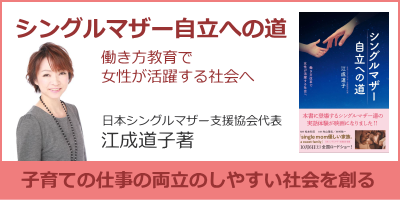【厳選】ママスマ編集部 おすすめ書籍を紹介
新たな生活に踏み出したシングルマザーの私たち。しかし、足元を見ればお金、教育、仕事、養育費などなど、不安と悩みは尽きません。それらの悩みに対し各方面の専門家、そして先輩たちが、書籍を通してたくさんの知恵を提供してくれています。ママスマ編集部では、そんな知恵とアドバイスの詰まった書籍を厳選、内容を抜粋して紹介してまいります。
「払えない」のか「払いたくない」のか
さて、世帯類型別、離婚の種類別に養育費の取り決め状況とその受給状況を見たので、つぎに、養育費の取り決めがあった場合にも支払いがおこなわれていない問題について考えてみたい。支払っていないということは、「払えない」か「払いたくない」かのどちらかだろう。
先に紹介した周の研究「離婚と養育費」では「JILPT 母子世帯調査2007」を用いて、離別父親の平均年収が376万2000円と一般世帯主の平均収入(520万円)より3割程度低いことが示されている。加えて、離別した父親の年収分布が一般世帯の収入分布よりばらつきが大きいこと│すなわち、年収300万円未満の低所得層が全体の37.2%(一般世帯だと27.0%)である一方で、年収1000万円以上の層も多い—ことも示した。
年収1000万円以上の父親であれば、養育費を支払っているのかも分析されているので紹介したい。年収が200万円以上300万円未満では、支払い率が23.6%である一方で、800万円以上1000万円未満では52.2%まで上昇するなど、父親の所得階層が上昇するのと比例して養育費の支払い率も高くなっている。
また、その養育費額についても、1000万円以上の所得の父親は、平均して月に5.69万円と、他の所得階層より高い養育費を支払っている。それでも、養育費の支払い率はどんなに高くても約50%であり、養育費金額も6万円程度というのは、なかなか驚くべき比率及び金額である。
さてこのように低い養育費の理由は二つある。
第一に、養育費の金額については、裁判官らによって作成された養育費「算定表」を基準として算定される。これは複雑な養育費計算を簡便にしたもので、実務の場面ではひじょうに役に立っているのだが、算定表が作られた当時とは所得水準・生活様式・消費構造などが変化しているので、現在の生活に見合うように計算方法について見直しが2019年12月におこなわれたばかりである。
もう一つは、大石亜希子「離別男性の生活実態と養育費」(2012年)による分析を紹介したい。これまで多くの先行研究によって母子世帯の所得水準や収入の分布について実態を知ることができている。しかし、調査やデータの性質上、離別父親を特定することが困難だったために離別父親の所得水準や収入の分布はこれまで知られていなかった。
そこで離別父親の経済的状況を扱った大石の研究はひじょうに有用である。大石によれば、一般の父親のうち本人の年収が350万円未満の割合は2割強にとどまるのに対し、離別再婚父親は3割以上が、また、離別単身父親では5割以上が本人年収350万円未満である。離別単身父親はとくに低所得で、2割弱が年収140万円未満である。
離別父親の再婚率は59.2%(169人中100人)であることと、単身の離別父親にくらべ、再婚した離別の父親は年収の高い層に偏っていることが背景にある。高所得層の父親の養育費の支払い率は約半分ということをあわせて考えれば、「昔の家族」の面倒まで見ていられない、というふうにとらえている人はいないだろうか。
まとめると、貧困層の父親は「自分の生活さえままならず、払えない」、比較的金銭的に余裕のある父親は「支払えるが、新しい家族の生活がある」ために、総じてどの所得層の父親においても、養育費を支払わないという状況が生み出されていると言えよう。
養育費を確保するための取り組み
さて、養育費を支払わない問題についてどうすべきか。子どもを実際に育てているもの(多くの場合は母である)にさらなる負担を強いるべきだとは言えないし、養育費金額の基礎となっている養育費の算定表について見直しを期待するところではあるが、支払っていない「義務者」(子を監護していない親)にきちんと支払いを求めたいところである。
しかし、大石が指摘・提案するように、離婚後ひとり身の父親は自分の生活でいっぱいいっぱいだし、余裕のある父親は再婚してしまって生活費の多くをそちらに振り分けないとならない。我が国には一律に養育費を徴収する制度は存在していない。なお、アメリカでは、「義務者」の捜索、養育費の天引きなどが公約制度としておこなわれている。
すると、子の親に、確実に養育費の支払いを取り付けるためにはどうするべきか考えなくてはならない。2003年および2004年には民事執行法の改正がおこなわれ、養育費の強制執行について給料等の差し押さえが可能となった。現在では、家庭裁判所で養育費について取り決めた場合や、取り決めを公正証書等で法的に有効にしている場合に限って、家庭裁判所の「履行確保制度」と民事執行法に基づく「強制執行制度」が利用できる。養育費の取り決めをせずに協議離婚した場合や、公正証書を作成していない場合には、家庭裁判所に養育費請求の申し立てをしたほうがいいだろう。
しかし、下夷美幸「養育費問題からみた日本の家族政策」(2011年)が指摘するように、困っているから養育費請求の申し立てをしたのに、それらの金銭的負担はすべて「権利者」(子を監護している親)の方に降りかかってくることを考えれば、現実的な手段とは言いにくい。
もっとも、我が国では、子どもがいる場合でさえ離婚届を提出してしまえば離婚が成立するが、アメリカ、イギリス、ドイツでは子どもの監護、面会交流、養育費の取り決めについて双方の親が責任を果たせるように、裁判所などが仲介する制度が存在する。
日本では2007年には「養育費相談支援センター」が創設され、養育費に関する情報提供や相談などをおこなっている。さらに先駆的な以下のような例もある。2014年に明石市が、離婚を検討している夫婦に、養育費や面会交流の頻度など子どもの養育方針の取り決めを促すことを目的として始めた取り組みで、「子ども養育支援ネットワーク」を設立し、効果がじわじわと浸透しつつある。
しかし、目下、養育費の確保は当人や裁判所に委ねられているので、子ども養育支援ネットワークも抜本的な解決にはまだ至らないようである。したがって、養育費について取り決めをしなくても離婚ができてしまう離婚制度そのものにも見直しが必要だという観点から養育費徴収制度を考え直すことが必要だろう。
児童扶養手当から総合支援への転換
本章は離婚によりひとり親となった世帯をどのように支援するかを考えるため、まず家族という側面から検討した。つぎに政府による制度はどうだろうか。これには、児童扶養手当が該当する。筆者らとしては児童扶養手当による支援を推したい。これは母子世帯だけでなく父子世帯(2010年8月から対象となった)も、離婚によるひとり親世帯だけでなく、未婚のひとり親世帯も対象となる。したがって、親の事情によらず子どもを社会で育てることとなる。
しかし、2000年代以降日本のひとり親世帯に向けた施策は、2002年の「母子及び寡婦福祉法」の改正を皮切りとして、児童扶養手当中心の支援から、就業・自立に向けた総合支援に転換して、経済的な支援を削減する方向に向かっている。
具体的には、養育費の額の8割が所得に算入されたり、手当自体が減額されると同時に就労支援事業が開始されたりしている。すなわち「福祉から就業へ」のスローガンを掲げたのである。したがって、政府からの保障を考えようとするときに、ひとり親世帯の仕事の状況も合わせて考える必要があるので、次章にて詳しく説明する。
家族の多様なあり方に対応するために
二人で話し合って離婚を決定するなかで、養育費について冷静に話し合うことは難しい。離婚のときに、養育費の取り決めをしなかったことを後悔しなかった人はいるのだろうか。
ひとり親世帯の立場を汲み取ってきた周『母子家庭の母への就業支援に関する研究』(2008年)や下夷「養育費問題からみた日本の家族政策」(2011年)が提案するような、養育費について仲裁してくれる機関の設立や、法的サービスの利用がさらに一般的になることが望ましい。さらには、養育費について取り決めをしなくても離婚ができてしまう離婚制度そのものにも見直しが必要だろう。
また、本章では離婚によってひとり親世帯となった親子に焦点を当てたが、周「離婚と養育費」(2012年)が指摘するように我が国の母子世帯率は国際的にみれば低い。2016年時点でも、2%に満たない程度である。
しかし、2005年から2010年にかけて未婚母子世帯は4万3000世帯増加しており、その増加率は48.2%であるという報告もある。葛西(2017年)も指摘しているし、ひとり親世帯になった理由について経年変化を見た、既出の表6-1でもわかるが、2011年以降、未婚母子世帯が死別母子世帯の割合を上回っている。ひとり親世帯が今後も増加する傾向にあるとすれば、家族の多様なあり方に対応できるように施策を講じる必要がある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
【著者】橘木 俊詔(たちばなき・としあき)
1943年、兵庫県生まれ。67年、小樽商科大学商学部卒業。69年、大阪大学大学院修士課程修了。73年、ジョンズ・ホプキンス大学大学院博士課程修了(Ph.D)。79年、京都大学経済研究所助教授。86年、同大学同研究所教授。2003年、同大学経済学研究科教授。この間、INSEE、OECD、大阪大学、スタンフォード大学、エセックス大学、London School of Economicsなどで教職と研究職を歴任。07年より、同志社大学経済学部教授、元日本経済学会会長。
【著者】迫田さやか(さこだ・さやか)
1986年、広島県生まれ。2009年、同志社大学経済学部卒業。11年、同大学経済学研究科博士前期課程修了、同後期課程入学。同大学ライフリスク研究センター嘱託研究員も務める。