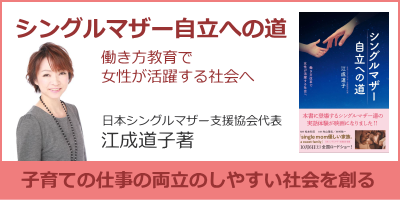これから養育費を受け取る予定の人、あるいはすでに養育費を受け取っている人の中には、養育費の受け取りに税金がかかるのか気になっている人もいるでしょう。原則、養育費の受け取りに税金がかかることはありませんが、例外的に課税されてしまうケースがあります。そこで、養育費に税金がかかる具体的なケース、税額をシミュレーションしていきますので、本記事を参考に養育費の税金について理解を深めていきましょう。
養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。
●養育費を確実に受け取りたい
●パートナーと連絡を取りたくない
●未払いが続いた時の手続きが心配
こうした養育費の未払い問題を解決する方法に「養育費保証サービス」があります。
養育費保証PLUSでは、業界最安(*)の料金で最大36か月の保証を提供しています。その他、連帯保証人がいなくても住まいや仕事探しのサポートも充実していますので、ぜひご検討ください。
*2023年4月時点
原則として養育費の受け取りに税金はかからない

原則、元配偶者から受け取る養育費には税金がかかることはありません。なぜかというと、養育費は子どもが生活費や医療費などで困ることがないように、法律上の「扶養義務」に基づいて支払われるものだからです。この点について所得税法と相続税法では以下のように記されています。
所得税法9条1項15号
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの『給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。』を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
上記の内容から「元配偶者より受け取る養育費は子どもの学資に充てるためのものなので所得税はかからない」と判断することができます。
また、相続税法についても以下の記述があります。
相続税法第21条の3 第1項2号
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
つまり「元配偶者より受け取った養育費が目的通りに使用されていれば課税対象とはならない」と解釈することができます。
養育費の受け取りに税金が発生するケースとは
養育費の受け取りは原則として課税されることはないと述べましたが、例外もあります。具体的には以下のようなケースでは課税対象となる場合があります。
・養育費を一括で受け取る場合
・高額な現金や資産を受け取る場合
・子どもの養育以外の目的でお金を使う場合
子どものために受け取る大切なお金ですから、課税されて実際の受け取り額が少なくなってしまう事態は避けたいものです。そこで、課税されるそれぞれのケースについて詳しく確認していきましょう。
養育費を一括で受け取る場合
養育費の受け取りは分割と一括の2つの方法がありますが、一括で受け取る場合は、上で紹介した相続税法21条3項5号の記述にある「通常必要と認められるもの」に該当しなくなることがあり、結果として税金を支払わなくてはならない可能性があります。
「途中で支払ってもらえなくなるかもしれない」「できればもう連絡を取りたくないからまとめて受け取っておきたい」などという思いから、一括受け取りを選択するケースが少なくありません。一括で受け取るとなるとまとまった金額になるため、受け取った後は金融機関へ預金することが一般的です。
しかし、その預金は本当に子どもの学資のために使われるのか第三者からは判断することが難しいのが現状です。そのうえ、金額も大きくなるために、贈与税がかかるかどうかの判断基準である「社会通念上、適当と認められる金額」を超え、結果として贈与税が課税されてしまう可能性があるのです。
◆養育費を分割払いで受け取る場合の平均相場について知りたい場合は、こちらの記事がおすすめです。
└離婚後に受け取れる養育費相場|年収や子どもの人数別に計算
高額な現金や資産を受け取る場合
毎月定額の養育費を受け取るのとは別に、たとえば養育費の支払者が子どもに対して大学入試に合格した記念に高級なスーツやブランド物の時計をプレゼントした、運転免許を取得したお祝いに車を買ってプレゼントしたというケースは贈与税の課税対象になる可能性があります。
なぜかというと、高級なスーツや車、ブランド物の時計などは「生活に必要なもの」には該当せず、先述した相続税法にある「通常必要と認められるもの」には含まれないからです。そのため、支払者である元配偶者から受け取るプレゼントは高額すぎるものではないか、内容に気を付ける必要があります。
子どもの養育以外の目的でお金を使う場合
受け取った養育費を子どもの養育費以外に使用してしまうと課税対象となります。たとえば、住宅購入資金に充てた、株を購入したという場合は「子どもの養育費に必要なもの」とはみなされません。このケースも先述した「通常必要と認められるもの」に該当しなくなるので、課税対象となってしまいます。
贈与税の課税額の計算方法
では、養育費に贈与税がかかる場合、どのくらいの金額を税金として支払うことになるのでしょうか。具体的にシミュレーションをしてみましょう。
また、例外として「教育資金の一括贈与による非課税制度」があるため、これについては本項の後半で解説します。
計算方法とシミュレーション
贈与税は以下の計算式で算出します。
贈与税=(贈与額-基礎控除110万円)×税率
「贈与額」は養育費として受け取った金額の合計額で、そこから基礎控除の110万円を差し引いた金額が「課税価格」になります。その課税価格に税率をかけた金額が贈与税として納める金額です。
また、贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分かれ、それぞれ税率が異なります。詳しくは下表をご覧ください。
| 贈与財産の種類 | 対象 |
|---|---|
| 一般贈与財産 | 「特例贈与財産用」に該当しない場合に適用。 例:兄弟間の贈与や夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など |
| 特例贈与財産 | 直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の者(子・孫など)への贈与。 例:祖父から孫への贈与、父から子への贈与など(夫の父からの贈与等は不可) |
つまり、子どもが未成年の場合は支払者から受け取る養育費は「一般贈与財産」に該当し、子どもが20歳以上の場合は「特例贈与財産」に該当する、ということです。
では、具体例を用いて贈与税のシミュレーションをしていきましょう。
【シミュレーションケース】
・養育費として一括で600万円を受け取る(毎月5万円×10年間分 )
・子どもは未成年
毎月5万円を10年間受け取ると合計で600万円となるため、それを一括で受け取る場合の贈与税を計算します。未成年の子どもだと一般贈与財産となるため、税率は一般税率が適用されます。先ほど紹介した【贈与税=(贈与額-基礎控除)×税率】に当てはめていきます。
税率は基礎控除後の課税価格を求めてから決まるため、まずは課税価格を計算します。
【課税価格=贈与額-基礎控除】であるため、贈与額600万円-控除110万円=課税価格490万円となります。
下の表のように課税価格によって税率と控除額が変わるため、課税価格490万円はどこに該当するのか見ていきましょう。
<一般税率>
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁 – No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
課税価格490万円は「600万円以下」の欄に該当するため、税率は30%、控除額は65万円となります。
贈与税=490万円×30%-65万円
=82万円
したがって、600万円の養育費を一括で受け取る場合、納めなければならない贈与税は82万円ということになります。
贈与税は数ある税金の中でも比較的税率が高いといえるものの、600万円の養育費のうち82万円を税金で支払うとなると、子どものための大切なお金が不足してしまう可能性があります。そのため、できるかぎり贈与税は支払わなくて済むよう、養育費の受け取り方法を選択していく必要があるでしょう。
ただし例外として教育資金の一括贈与による非課税制度あり
先ほどシミュレーションしたように、贈与税の課税対象となったら納める税額は高額になるといえますが、実は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を利用すると、養育費を一括で受け取っても最高1,500万円までを非課税にすることができます。
| 対象となる子ども | 受贈者は満30歳に達するまでの個人 ※令和5年3月31日まで適用期間が延長 |
| 贈与する人 | 直系尊属(父母や祖父母のほか、養子縁組をした親) |
| 教育資金の用途 | ①学校等へ直接支払う金銭 ※入学金、授業料、保育料、修学旅行費、学校給食費など ※学校等とは幼稚園、保育所、小・中学校、高校、大学など ②学校等以外の者へ直接支払う金銭(上限は500万円) ※学習塾や各種教室へ直接支払う金銭・使用料など |
| 契約・利用方法 | 利用の流れは、 ①金融機関と「教育資金贈与信託」契約を結んで、教育資金口座を開設する ②必要時に払い出しを行う(学校などからの領収書を提出) ※受贈者が30歳に達する等、いくつかの条件より契約終了 |
この制度を活用すると、最高1,500万円までなら一括で受け取っても非課税扱いにすることができます。500万円という上限はあるものの、習い事や塾の費用といった「教育資金以外」のものに利用できるのも大きなメリットのひとつです。
ただし、教育資金以外に利用した金額や30歳になるまでに使いきれなかった金額には贈与税がかかってしまうのでご注意ください。
養育費の税金に関する質問と回答
養育費の税金に関する質問と回答として、ここでは養育費を投資・運用に回した場合、学資保険の支払いに充てた場合の課税について紹介していきます。
子どもの将来のために養育費を投資・運用すると課税される?
子どもの教育資金を貯める方法のひとつに「NISA」や「つみたてNISA」があり、たとえば養育費を一括で受け取るなら「NISA」、毎月受け取るなら「つみたてNISA」といったように運用にまわすこと自体は可能です。
しかし、養育費をこういった投資商品で運用する場合、たとえそれが子どもの学資のためであっても課税対象となります。これは、投資や運用は「生活費や教育費として必要なもの」とは認められないためです。
ちなみに、NISAやつみたてNISAが非課税となるのは「分配金」や「譲渡益」です。NISAは毎年120万円を限度に5年間で最高600万円までが、つみたてNISAは毎年40万円を限度に20年間で最高800万円までが非課税となります。
養育費における相続税や贈与税の非課税への取り扱いと、NISAなどによる分配金や譲渡益の非課税への取り扱いは別になるためご注意ください。
養育費を使って学資保険に申し込んだ場合はどうなる?
学資保険は子どもの将来の学資に充てるものなので、養育費を保険料に充てても税金がかからないようなイメージがありますが、学資保険はあくまでも貯蓄性のある「保険商品」であるため課税対象となります。
なお、学資保険には「離婚前から加入していた場合」と「離婚後に加入する場合」に分かれ、それぞれのケースで対応が異なります。
離婚前から加入していた場合
離婚前から学資保険に加入していた場合は、夫婦の「共有財産」として扱われるため、仮に離婚となったら中途解約してそこから得た解約返戻金を夫婦間で分け合うケースが多く見られます。
しかし、貯蓄性のある保険商品を中途解約すると元本割れする可能性が高いため損してしまううえ、子どもの将来への学資に備えることができなくなってしまいます。そのため、離婚するとなっても学資保険は中途解約せず、保険料の支払いについて歩み寄った話し合いが必要になるといえます。
離婚後に加入する場合
先述のとおり養育費から学資保険の保険料を支払うと課税対象となるため、養育費と学資保険は別々に考える必要があります。
学資保険は親権者が契約者となって保険料を支払うので、加入する場合は家計を圧迫しないよう無理のない保険料に設定するようにしましょう。もし可能であれば、離婚協議の際、養育費に学資保険の保険料を上乗せして支払ってもらえるかどうかについて話し合っておくと良いでしょう。
支払者側の養育費の税金について
立場を変え、養育費を支払う側の税金はどうなるのか説明していきます。養育費の支払者は、年末調整や確定申告の際に「扶養控除」を適用することで税金が安くなる可能性があります。
離婚後も養育費を支払っていれば子供を扶養に入れられる
離婚してから子どもの養育費を支払い続けている場合、子どもを扶養親族に入れることができるので、年末調整や確定申告で「扶養控除」を適用できるようになります。
なお、「扶養控除」とは「所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、一定金額の所得控除が受けられる」制度のことですが、すべての子どもが控除対象扶養親族になるわけではありません。
・扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上
・年間の合計所得金額が48万円以下
・納税者と生計を一にしている
この3つの条件を満たしている子どもが控除対象扶養親族に該当します。
また、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の子どもを「特定扶養親族」といい、さらに控除額が優遇されます。
| 区分 | 年齢 | 控除額 |
| 控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
中には、離婚して子どもと別居しているのだから「生計を一にしている」とはいえないのでは?と感じる人もいるのではないでしょうか。
実は、国税庁によると、養育費の支払いが「扶養義務」の履行として「成人に達するまで」といった一定の年齢に限って行われる場合は、その期間は原則として「生計を一にしている」ものとみなされることから、元配偶者は子どもを扶養親族に入れることができるとされています。
扶養控除を受ける場合の注意点
扶養控除を受けられると税金が安くなる可能性があるため、中には養育費の支払者と受取者の両方が子供を扶養に入れようとするケースがあります。しかし、扶養控除はいずれか片方の親にしか適用されないため、離婚協議ではどちらに適用するのか必ず話し合っておく必要があります。
ちなみに、もし両方の親がそれぞれ子供を扶養に入れて重複してしまった場合は、どちらか片方に税務署から追徴課税される可能性があります。一般的には、早く申告したほうの親に扶養控除が適用されることが多いですが、場合によっては所得が多いほうに適用されることもあります。こういったトラブルを避けるためにも、事前に夫婦間で扶養控除について話し合っておくと安心です。
また、繰り返しとなりますが、扶養控除となるのは「16歳以上の子ども」のみで、16歳未満の子どもは対象外となる点にも注意が必要です。
養育費を一括で受け取る場合は贈与税の対象になることに気をつけよう
養育費の受け取りには原則として税金はかかりませんが、例外的に「一括で受け取る場合」「高額な現金や資産を受け取る場合」「養育以外のことでお金を使う場合」には贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
贈与税は比較的税率が高く納税負担が大きくなることから、子どもの将来の大切な学資が不足することのないよう、養育費の受け取り方については慎重に検討することが求められるでしょう。
養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。
養育費保証PLUSで未払いの不安を解消!
養育費保証PLUSの特徴
● しっかりと養育費を受け取りたい
● 保証期間は長い方が嬉しい
●弁護士費用や法的手続き費用を負担して欲しい
●シングルマザーでも子どもの将来をしっかりと支えたい
このようなお悩みを解決するために、「養育費保証PLUS」では業界最安(*)の保証料金で養育費の未払いを防ぎます。無料相談も承っていますので、まずはぜひ資料をダウンロードください。
*2021年7月時点